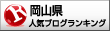読書の秋(後編)
それでは「読書の秋」後編。
まずは…
御子柴善之「自分で考える勇気 カント哲学入門」
アーレントやルソーをはじめ、あらゆるところに顔を出すカントの道徳哲学。
一度きちんと勉強しておく必要があると思いながら、いきなり三批判書(純粋理性批判、実践理性批判、判断力批判)に当たるのはハードルが高い。
ということで、中学生向けの「岩波ジュニア新書」から。
とは言え、出来るだけ簡単な言葉をチョイスしつつも、レベルの高いことが書いてあります。
中学生がきちんと読みこなせるのか疑問(笑)
岩波ジュニア新書は総じてレベルも質も高いものが多いですね。
仲正昌樹「今こそルソーを読み直す」
読んでいたのがちょうど選挙のときで、民主政という政体について根本から勉強してみたくなったので。
民主政について語るならルソーは避けて通れない。
憲法について語るならルソーの社会契約論くらい読みこなせないと、とは思う(だからと言って、ルソーが正しいとか言うつもりは無いけど)。
仲正先生の解説は分かり易くて好きです。
言わずと知れた漱石前期三部作の一作目。
漱石漫談に触発されて再読。
以前(学生のころ?)読んだときには何が面白いのかさっぱり分からなかったけど、今回そこそこ楽しめたのは、作品が書かれた当時の時代背景のことなどが昔よりも分かってきたからなのかなと思う。 nishigawa0323.hatenablog.com
息抜きに読みました。
副島氏の本は初めて読みましたが、すごい陰謀論者ですね。
私にはどこまで真実なのかよく分かりません。
いつもどおりの独特の視点で面白く読ませていただきました。
大事な指摘が随所になされています。
なぜ日本で天皇制(あえてこう呼ばせていただきます)が続いてきたのかについて考える一助になると思います。
天皇制なんて無くても困らないんじゃないの?という方に是非読んでもらいたい。
橋爪大三郎「正しい本の読み方」
たまに読んでしまう「本の読み方」の本。
たいして目新しいことは書いてなかったけど、自分の本の読み方を自省する機会にはなった。
読むべき本のリストは参考にさせていただきます。
今年中にロシア革命史のことを一通り学んでおきたいと思い手に取りました。
言うまでもなく、2017年はロシア革命(2月革命及び10月革命)から100年目に当たります。
1917年→ロシア革命というのは、中学校の歴史でも年号を丸暗記するような世界史上の超重要イベントであるにもかかわらず、実際に何が起こったのかということについてはほとんど知りませんでした。
ロシア革命史を勉強すると、20世紀の歴史がよく見えるようになります。